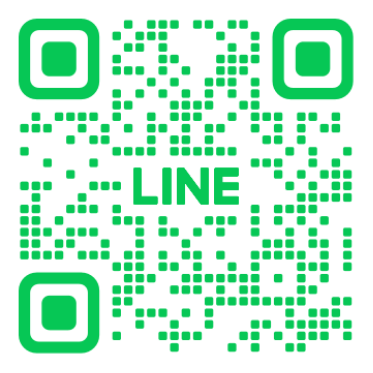57.新車メンテナンスパックとは?必要性と選び方を徹底解説
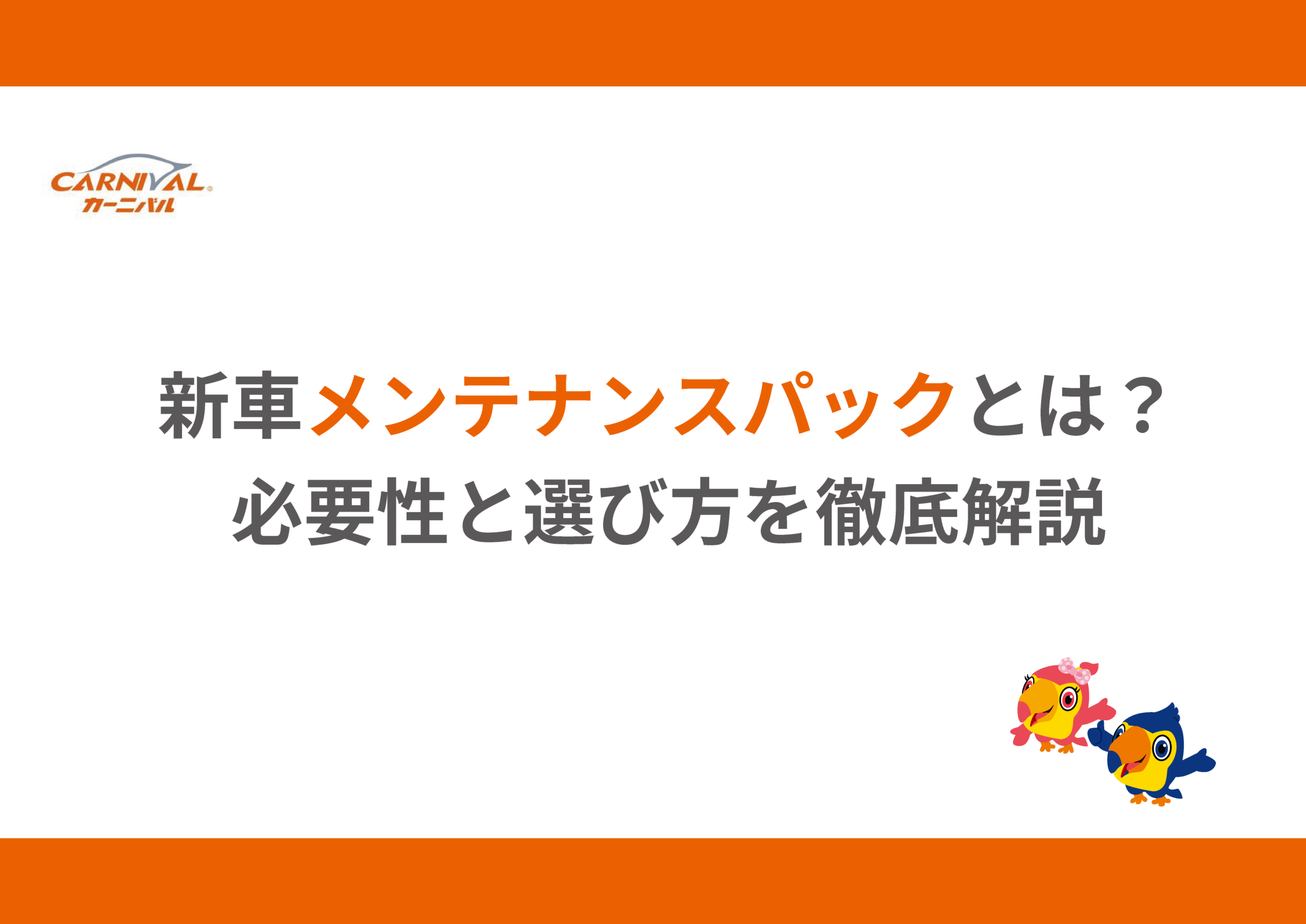
新車メンテナンスパックとは?必要性と選び方を徹底解説
新車を購入する際、ディーラーから「メンテナンスパック」への加入を勧められることがよくあります。
しかし、多くの方が「本当に必要なのか」「費用はどのくらいなのか」といった疑問を抱くのではないでしょうか。
本記事では、新車のメンテナンスパックについて詳しく解説し、あなたの疑問を解決いたします。
新車メンテナンスパックの基本概要
新車のメンテナンスパックの仕組みと含まれるサービス内容を理解することで、適切な判断ができるようになります。
車両の適切な維持管理を行うために必要な知識を身につけましょう。

新車のメンテナンスパックとは、車検や定期点検、消耗品交換などのアフターメンテナンスをひとつにまとめたパッケージサービスです。
新車購入時に加入することで、将来必要となる整備費用を事前に支払い、定期的なメンテナンスを計画的に受けることができます。
一般的には新車購入から3年間または5年間といった期間設定で、その間に必要となる点検や整備がパッケージ化されています。
国土交通省の自動車点検基準によると、自家用乗用車の場合は1年ごとに29項目、2年ごとに60項目の法定点検が義務付けられています。
(参考:国土交通省「点検整備の種類」)
メンテナンスパックには、これらの法定点検に加えて各種消耗品の交換が含まれることが一般的です。
具体的には、法定12ヶ月点検、6ヶ月ごとの定期点検、初回車検のほか、エンジンオイル交換、オイルフィルター交換、ワイパーゴム交換、エアコンフィルター交換といった消耗品のメンテナンスも含まれる場合があります。
メンテナンスパックのメリット・デメリット
メンテナンスパックの加入を検討する際は、メリットとデメリットの両面を十分に理解することが重要です。
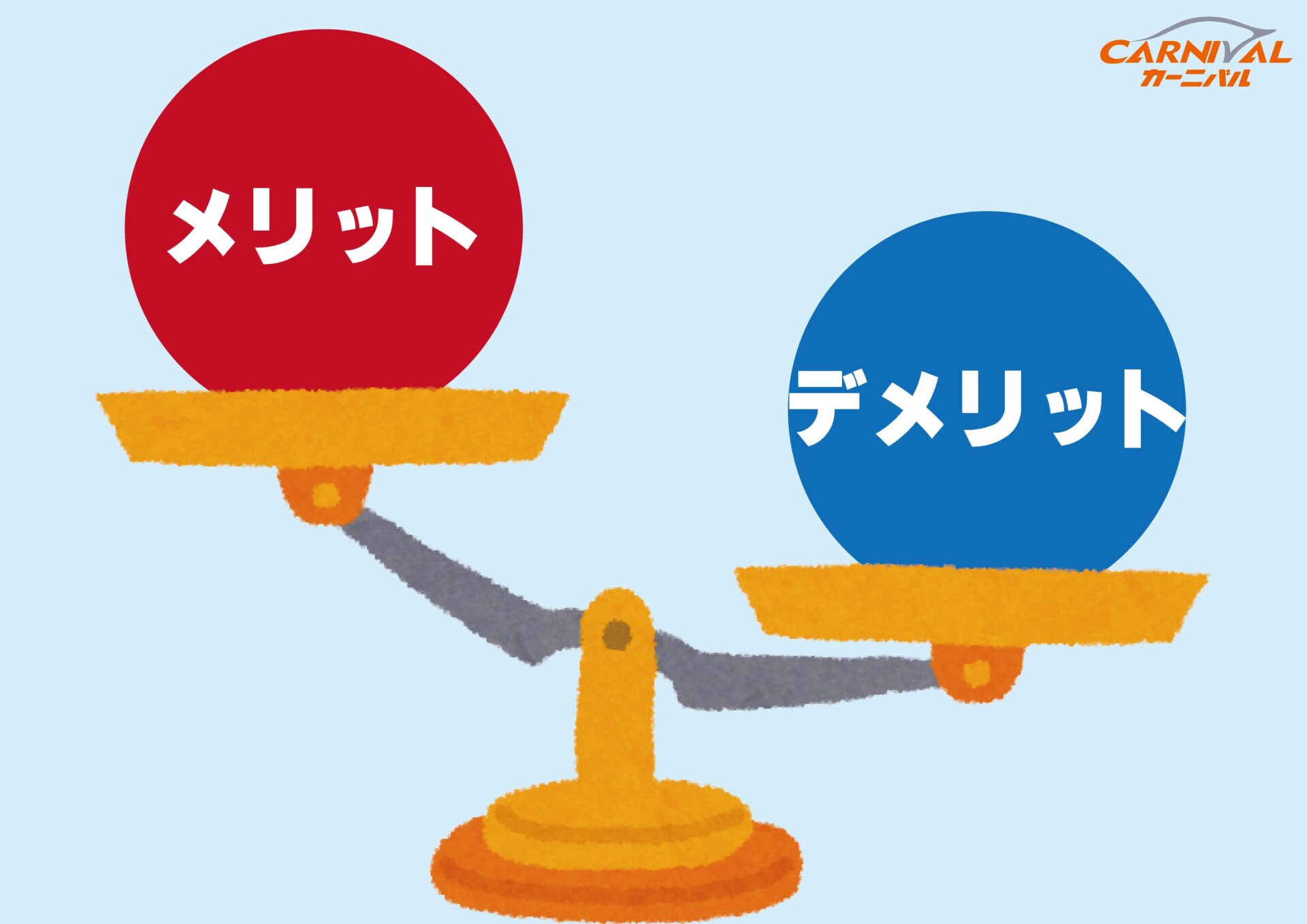
メンテナンスパックに加入する最大のメリットは、車両の安全性と信頼性を専門的な視点から継続的に維持できることです。
自動車は走行距離や時間の経過とともに劣化・摩耗する部品等が多く使用されているため、その性能や耐久性は走行距離や時間の経過とともに低下するとされています。
定期的な点検により、素人では発見しにくい不具合や故障の前兆を早期に発見できるため、重大なトラブルを未然に防ぐことができます。
経済的なメリットとしては、突発的な出費を避けることができ、年間の車両維持費を計画的に管理することが可能になります。
一方で、メンテナンスパックにはいくつかのデメリットも存在します。
最も大きな課題は、契約時にまとまった費用を一括で支払う必要があることです。
また、走行距離が少ない方にとって頻繁なオイル交換は過剰なサービスとなり、結果的に割高な費用を支払うことになる可能性があります。
メンテナンスを受ける場所が契約したディーラーに限定されることも、人によってはデメリットとなります。
法的義務と点検の重要性
車両の点検・整備には法的な義務があり、適切な実施が求められています。
国の定める基準を理解し、安全な運転のための知識を身につけましょう。
道路運送車両法第47条により、自動車の使用者は「自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない」と定められています。
(参考:国土交通省「点検整備の必要性・重要性」)
さらに道路運送車両法第48条では、自家用乗用車について定期的な点検の実施が義務付けられています。
国土交通省では、点検整備を行わないと走行中に故障や、排出ガスの増加、燃料の浪費等を招きかねないとして、適切な維持管理の重要性を示しています。
車検はあくまで検査時点での安全・環境基準への適合を確認するものであり、その後の有効期間中の安全性を保証するものではありません。
したがって、自動車ユーザーは法令に基づき、日常点検や定期整備を継続的に実施する義務があります。
点検整備を怠ると、たとえ車検に合格していても、安全性や性能の低下につながる可能性があるため注意が必要です。
メンテナンスパックが必要な人・不要な人
メンテナンスパックの加入判断は、個人の車の使用状況や知識レベルによって大きく異なります。
自分の状況に当てはめて、最適な選択を行ってください。
メンテナンスパックの加入をおすすめするのは、車の整備に関する知識が少なく、自分で適切な点検時期を判断することが難しい方です。
道路運送車両法により車の使用者には点検・整備の義務が課せられていますが、専門的な知識が必要な作業も多く含まれています。
また、月間走行距離が多い方や、車を頻繁に使用する方も加入をおすすめします。
使用頻度が高いと部品の劣化も早くなるため、定期的な専門的チェックが安全性確保には不可欠です。
一方で、車に関する知識が豊富で、自分で適切なメンテナンス業者を選択できる方にとっては、メンテナンスパックは必ずしも必要ではありません。
走行距離が少ない方や、車の使用頻度が低い方も、パックのメリットを十分に活用できない可能性があります。
また、車の買い替えサイクルが短い方や、転居の可能性が高い方にとっては、長期契約のメンテナンスパックは向いていません。
選択時の重要ポイント
メンテナンスパックを選択する際は、契約前の確認事項と、自分の使用状況に合わせた選択方法を理解することが重要です。
適切な判断基準を身につけて、最適なプランを見つけましょう。

契約前には、含まれるサービス内容を詳細に確認することが重要です。
点検の回数や内容、交換される消耗品の種類、車検が含まれるかどうかなど、自分の使用状況に合ったサービスが含まれているかを精査しましょう。
料金体系についても、総額だけでなく、含まれないサービスや追加費用が発生する可能性について確認が必要です。
契約期間や解約条件についても必ず確認し、途中解約が可能な条件、解約時の手数料、未使用分の返金について明確にしておくことで、後のトラブルを避けることができます。
年間走行距離は、メンテナンスパック選択の重要な判断基準となります。
走行距離が多い場合は、消耗品交換の頻度が高くなるため、充実したサービス内容のパックを選択することで費用対効果を高めることができます。
車の使用目的も考慮すべき要素です。
通勤や業務で毎日使用する場合と、週末のレジャーでのみ使用する場合では、必要なメンテナンスの頻度や内容が異なります。
将来の計画も選択に影響します。
車の買い替え予定、転居の可能性、ライフスタイルの変化などを考慮して、契約期間や内容を決定しましょう。
新車のメンテナンスパックに関するよくある質問
Q1. 新車のメンテナンスパックは本当にお得?
メンテナンスパックは、点検・整備の費用をあらかじめパッケージ化しておくことで、突発的な出費を防げる点で経済的メリットがあります。
ただし、年間走行距離が少ない方や、あまり車を使わない方にとっては、必要以上の整備が含まれる場合があるため、使用状況に応じた判断が必要です。
Q2. メンテナンスパックに加入しないと、車検や点検は受けられない?
加入していなくても、ディーラーや整備工場で車検・点検を個別に受けることは可能です。
ただし、都度支払いや予約の手間がかかる場合もあるため、安心してメンテナンスを任せたい方にはパック加入がおすすめです。
Q3. 途中で引っ越した場合、メンテナンスパックはどうなる?
多くのディーラーでは、契約した店舗での点検が基本となるため、転居先で同じグループ店舗がない場合は対応できない可能性があります。
引っ越しの予定がある方は、事前に利用条件や解約ルールを確認することが重要です。
まとめ|あなたに最適なメンテナンスパックを見極めよう
新車のメンテナンスパックは、車両の安全性・信頼性を長期間にわたって維持するための有効な手段です。
国土交通省のデータでも、定期的な点検整備がトラブルや故障を未然に防ぐ効果があることが示されています。
車検だけでは保証されない“継続的な安全性”を確保するためには、法定点検や消耗品の交換を計画的に実施することが重要です。
とはいえ、メンテナンスパックの必要性は一律ではありません。
車の使用頻度や年間走行距離、車に関する知識の有無、経済状況、ライフスタイルの変化などを総合的に考慮したうえで、自分に合ったプランを選択することが求められます。
加入前には、サービス内容や料金体系、契約期間、解約条件などをしっかりと確認し、不明点があれば販売店に相談するのが安心です。
メンテナンスを外部業者に任せるか、パックで一括管理するかも含めて、メリット・デメリットを見極めて判断しましょう。
安心・安全で快適なカーライフを続けるために、日頃からの適切なメンテナンス計画は欠かせません。
新車を購入する際には、メンテナンスパックの活用も視野に入れて、長く快適に車と付き合っていけるよう準備しておくことをおすすめします。
カーニバルでの新車購入とアフターサポート
埼玉県内で4店舗を展開するカーニバルでは、新車購入から車検、整備まで、お客様のカーライフを総合的にサポートしています。
創業27年、累計30,000台以上の販売実績を持つ地域密着のカーショップとして、お客様一人ひとりの使用状況やライフスタイルに合わせた適切なアドバイスを提供いたします。
久喜インター店、岩槻店、上尾店、春日部店の各店舗では、新車販売はもちろん、車検や整備、自動車保険まで幅広いサービスを提供しており、メンテナンスに関するご相談も随時承っています。
新車購入をご検討の際は、メンテナンスパックの必要性も含めて、ぜひお気軽にご相談ください。
地域の皆様のカーライフに安心と安全を提供し続けることが、私たちカーニバルの使命です。

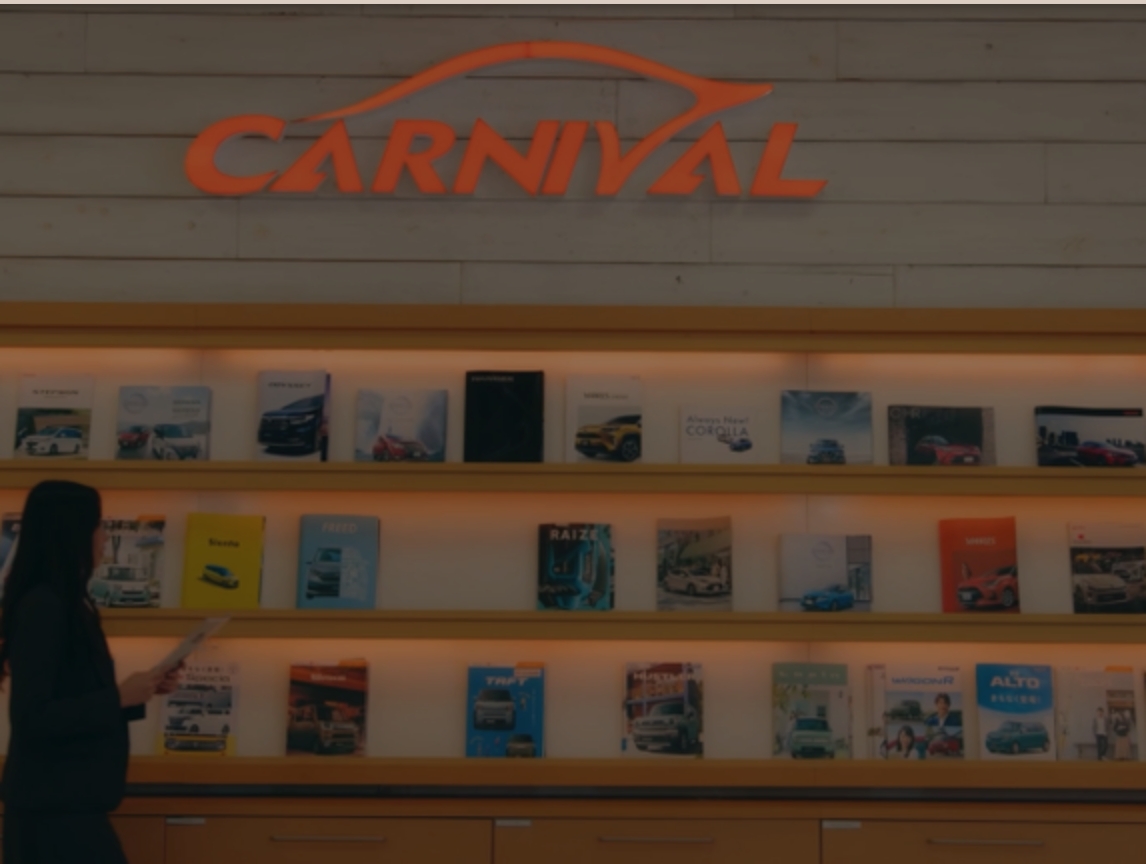
contact
お問い合わせ
お電話でのお問合わせ
最寄りの店舗に直接ご連絡お願いします
(受付時間:AM10:00~PM7:00)
メールでのお問合わせ
メールでのお問合わせはこちら