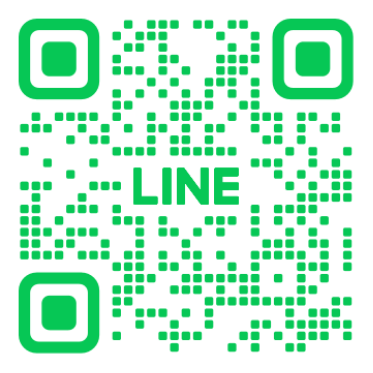42.新車の車検期間は何年?初心者でもわかる車検の基本知識と費用を徹底解説
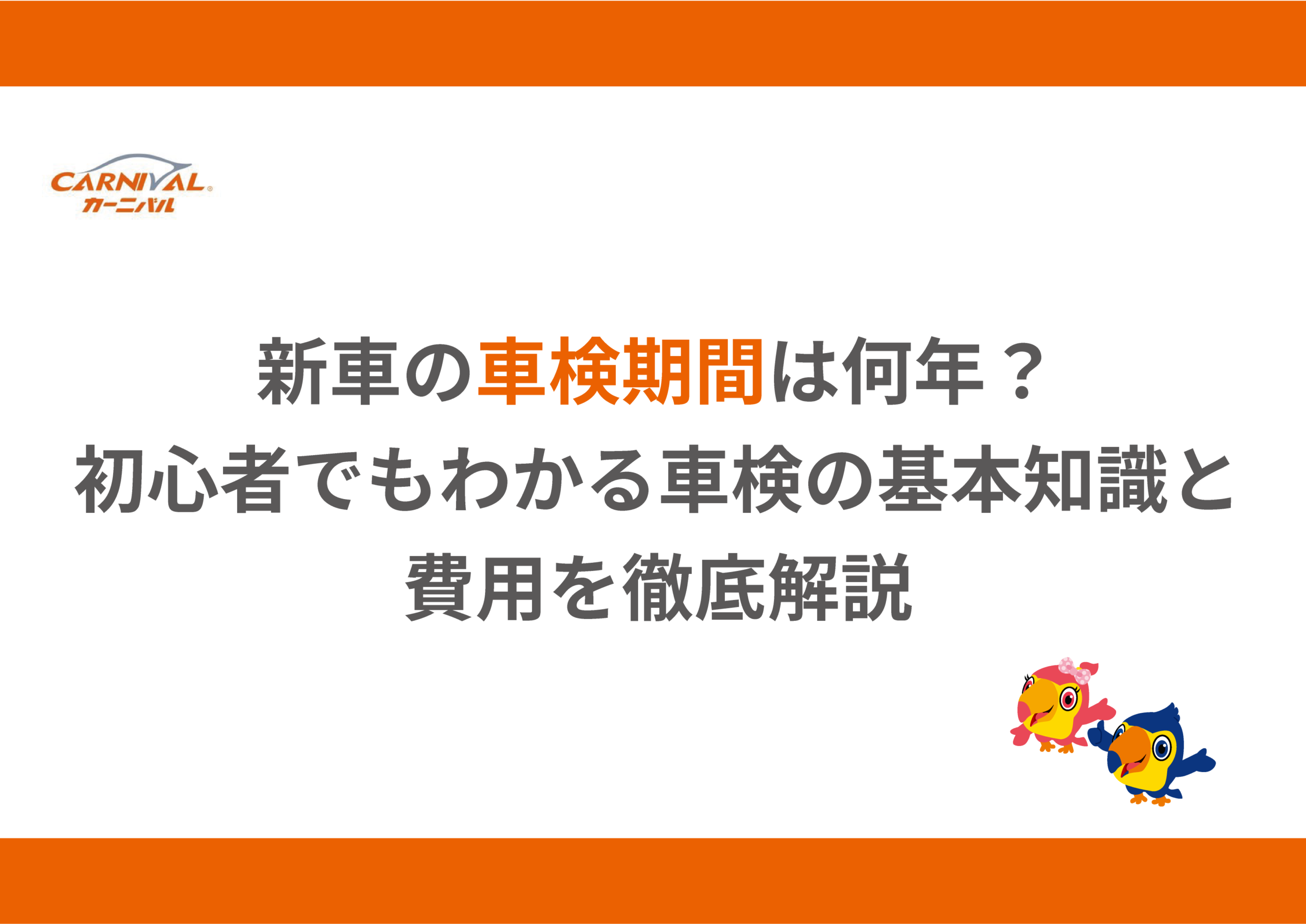
新車の車検期間は何年?初心者でもわかる車検の基本知識と費用を徹底解説
新車を購入した際に「車検はいつ受ければいいの?」「どのくらい費用がかかるの?」といった疑問を抱く方は多いでしょう。
車検は法律で義務付けられている重要な検査であり、適切な時期に受けなければ公道を走行することができなくなってしまいます。
この記事では、新車の車検期間について詳しく解説し、車検に関する疑問や不安を解消していきます。
新車の車検期間の基本ルール
新車を購入した方が最初に知っておきたいのは、車検をいつ受ける必要があるかということです。
一般的な新車の車検期間から、車種によって異なるケースまで詳しく解説していきます。

新車登録時の車検の有効期限は、自家用乗用車は新車登録から3年間です。
これは普通車(3ナンバー)と小型車(5ナンバー)の両方に適用される基本的なルールとなっています。
例えば、2025年5月1日に新車登録した車の場合、有効期限満了日は2028年4月30日となります。
新車の初回車検が3年間とされている理由は、新車は製造時に厳格な品質管理が行われており、登録時にも検査を通していることが挙げられます。
さらに納車前には整備が実施されているため、新車の状態では大きな不具合が生じる可能性が低いと考えられているためです。
道路運送車両法(第61条 自動車検査証の有効期間)に基づいて、車検の有効期間は法律で定められています。
(参考: JAF(日本自動車連盟)「車検の有効期間は何年ですか?」 )
軽自動車についても、基本的には一般的な乗用車と同様の扱いとなります。
5ナンバーの軽自動車も一般的な乗用車と同じく、初度登録(新車など初めての登録)の3年後が初めての車検となります。
乗用タイプの軽自動車(N-BOX、ハスラー、タント、ムーヴなど)は初回3年、その後2年ごとの車検となります。
一方、商用軽自動車である4ナンバーの軽自動車(軽トラック、軽バンなど)は初回から2年ごとの車検となるため、用途を確認しておくことが重要です。
車種によって異なる新車の車検期間
新車といっても、すべての車が3年間の車検期間を持つわけではありません。
商用車や特殊な用途の車両は、一般的な乗用車とは異なる車検間隔が設定されています。
新車の車検が2年になる車両は以下のとおりです。
自家用貨物自動車(白地に緑字)、自家用軽貨物自動車(黄地に黒字)、事業用軽貨物自動車(黒地に黄字)、大型特殊自動車(白地に緑字)、特殊用途自動車(白地に緑字)が該当します。
商用車や特殊車両は、一般的な乗用車よりも使用頻度が高く、走行距離も多くなる傾向があります。
そのため、安全性を確保するために短い間隔での車検が義務付けられています。
事業用として登録されている車両は、さらに厳しい車検間隔が設定されています。
8t以上の貨物自動車は新車登録から最初の車検までが1年間で、以降も1年ごとの車検となります。
8t未満の貨物自動車は新車登録から最初の車検までが2年間ですが、以降は1年ごとの車検が必要です。
事業用車両は商業活動に直結するため、故障による事故のリスクを最小限に抑える必要があります。
2回目以降の車検期間と継続車検
新車の初回車検を終えた後は、継続車検と呼ばれる定期的な車検を受ける必要があります。
継続車検では車両の状態がより詳細にチェックされ、部品の摩耗や劣化が進んでいるため交換が必要になることも多くなります。
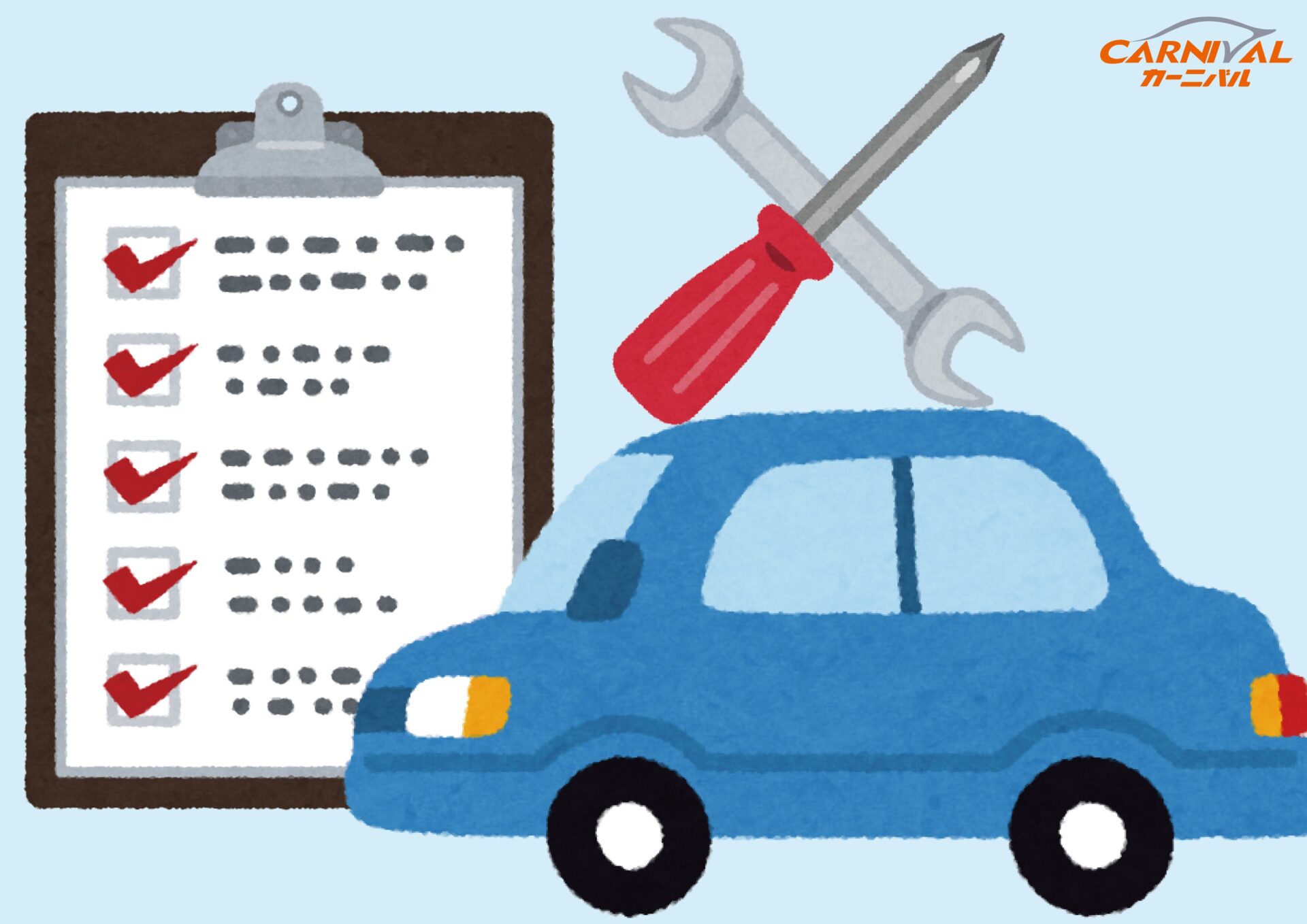
新車の初回車検を終えた後の車検は「継続車検」と呼ばれます。
自家用乗用車の継続車検の有効期間は、2回目以降は車種や車齢に関わらず2年間の有効期間が定められています。
これは軽自動車から大型車まで、自家用乗用車であれば共通のルールとなります。
継続車検では、車両の状態をより詳細にチェックする必要があります。
新車時とは異なり、部品の摩耗や劣化が進んでいるため、交換が必要な部品も出てくる可能性が高くなります。
以前は新車登録から10年以上経過した車両は毎年車検を受ける必要がありましたが、現在は制度が変更されています。
1995年の道路運送車両法の改正により、普通自動車の継続車検の有効期間は乗っている年数が何年経っても変わらず2年ごとになりました。
ただし、車は年数が経過するにつれて劣化や故障の可能性が高くなるため、車検の頻度は変わらなくても日常的なメンテナンスの重要性は増してきます。
なお、新車登録から13年経過すると自動車重量税が約2~4割増額されるため、車検費用が高くなる点には注意が必要です。
車検を受けられる期間とタイミング
車検はいつでも受けられるわけではなく、適切なタイミングがあります。
また、2025年4月1日からは制度が改正され、より余裕を持って車検を受けられるようになりました。
車検は車検証の有効期間満了日前であればいつでも受けることができますが、適切なタイミングがあります。
従来は「有効期間満了日の1か月前から満了日までの間」に受検する必要がありましたが、2025年4月からは制度が改正され、車検証の有効期間満了日の2ヶ月前から車検を受けることができるようになりました。
この期間内に車検を受ければ、既存の車検期間を無駄にすることなく新しい車検証に更新することができます。
国土交通省の発表によると、3月の車検は約389万台と他の月の月平均車検台数をはるかに超えており、車検の分散化が重要な課題となっています。
(参考: 国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~」)
車検は早く受けすぎると損をする場合があります。
有効期間満了日の2ヶ月以上前に車検を受けた場合、車検を受けた日から新たに2年間(または1年間)の有効期間が始まってしまうため、残っていた車検期間が無駄になってしまいます。
このような損失を避けるためにも、適切なタイミングでの車検受検が重要です。
新車の車検にかかる費用
新車の初回車検では、一般的に継続車検よりも費用が安くなる傾向があります。
車検費用の構成要素を理解しておくことで、適切な業者選びや費用の準備ができるようになります。
車検費用は大きく3つの要素に分けられます。
まず、どこで車検を受けても変わらない「法定費用」があります。
法定費用とは、自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料(印紙代)のことで、法律で定められているため業者による違いはありません。
次に、車検を依頼する業者によって異なる「車検基本料」があります。
これは点検料、整備料、代行手数料などが含まれており、業者選びによって大きく変わる部分です。
最後に、必要に応じて発生する「部品交換費用」があります。
新車の初回車検では部品交換の必要性が低いため、この部分の費用を抑えることができます。
法定費用の具体例として、軽自動車の継続検査の場合、自動車重量税6,600円、自賠責保険料17,540円、印紙代2,200円となります(エコカー減税適用なし・2025年現在)。
印紙代は検査実施場所により異なる場合があります。
新車の初回車検では、部品交換の必要性が低いことを活用して費用を抑えることができます。
まず、複数の業者から見積もりを取得して比較することが重要です。
ディーラー、整備工場、車検専門店、カー用品店など、それぞれ特徴や料金体系が異なります。
また、新車であれば車検前の事前整備も最小限で済むことが多いため、必要以上の整備を勧められた場合は本当に必要かどうかを確認することも大切です。
ただし、安全性に関わる部分については適切な整備を受けることが重要であり、単純に安いだけで業者を選ぶのではなく、信頼性も考慮して選択することが必要です。
車検切れのリスクと対処法
車検が切れた状態で公道を走行することは法律で厳しく禁止されており、重いペナルティが科せられます。
うっかり車検を忘れてしまった場合の対処法と、車検切れを防ぐための対策について解説します。
車検が切れた車で公道を走行した場合は、道路運送車両法108条により6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金、かつ交通違反にも該当するため、違反点数6点に加えて30日間の免許停止処分となります。
さらに、車検切れの車両は自賠責保険も切れている可能性が高く、この場合は別途自賠責保険法違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数6点が加算されます。
両方の違反を合わせると、合計12点の違反点数となり、免許停止期間がさらに延長される可能性があります。
車検が切れてしまった場合でも、適切な手続きを行えば車検を受けることは可能です。
ただし、車検切れの車両で公道を走行することはできないため、車検場まで移動するための特別な手続きが必要となります。
最も一般的な方法は、市区町村の窓口で仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を取得することです。
仮ナンバーを取得すれば、指定された期間・経路内に限り公道を走行することができます。
車検証と車検期間の確認方法
車検の有効期間を正確に把握することは、車検切れを防ぐための基本です。
車検証や車検シールから期間を確認する方法について説明します。

車検の有効期間は、車検証(自動車検査証)に記載されている「有効期間の満了する日」で確認することができます。
2023年1月以前に発行された紙の車検証では、車検証の下部にある「有効期間の満了する日」欄を確認します。
2023年1月以降に発行される電子車検証には有効期限が記載されていないため、国土交通省が提供する専用アプリ「車検証閲覧アプリ」を利用することで、有効期限をオンラインで確認できます。
フロントガラスに貼られている車検シール(検査標章)でも車検期間を確認することができます。
車検シールの表面(車外から見える面)に記載されている大きな数字が車検の満了月を、小さな数字が車検の満了年を表しています。
車検シールは外側からは年と月のみが見えますが、車内側からは詳細な満了日まで確認することができます。
日常的に車検期間を意識するためには、車検シールを定期的にチェックする習慣をつけておくことが効果的です。
新車の車検期間に関するよくある質問
Q1:車検の有効期限はどこで確認できる?
車検証の「有効期間の満了する日」または、フロントガラスの車検シールで確認できます。
Q2:新車の車検はいつ予約すべき?
2025年4月以降は、満了日の2ヶ月前から受けられるようになったため、混雑を避けて早めの予約がおすすめです。
まとめ|車検期間と計画的な受検の重要性を抑えよう
新車の車検期間について理解しておくことは、安全で法的な車両運行のために不可欠です。
一般的な自家用乗用車の場合、新車登録から3年後に初回車検を受け、その後は2年ごとに継続車検を受ける必要があります。
ただし、商用車や特殊車両では初回から2年ごとの車検となる場合があるため、購入時には必ず確認しておくことが重要です。
車検は単なる法的義務ではなく、安全な運転を維持するための重要な制度です。
適切な時期に車検を受けることで、車両の不具合を早期に発見し、重大な事故を防ぐことができます。
車検費用についても事前に理解しておくことで、計画的な資金準備が可能となります。
新車の初回車検は比較的費用を抑えることができる機会でもあるため、信頼できる業者選びと適切な時期での受検を心がけることが大切です。
2025年4月からは車検を受けられる期間が2ヶ月前からに延長されたため、より余裕を持って車検の計画を立てることができるようになりました。
カーニバルで安心のカーライフをサポート
埼玉県内で4店舗を展開するカーニバルでは、新車販売から車検、整備まで、お客様のカーライフを総合的にサポートいたします。
創業27年、累計30,000台以上の販売実績を持つ地域密着のカーショップとして、車検に関するご相談から新車・中古車の購入まで、お客様一人ひとりのニーズに合わせたサービスを提供しています。
車検についてのご質問や新車購入をご検討の際は、久喜インター店、岩槻店、上尾店、春日部店のいずれの店舗でも専門スタッフが丁寧にご対応いたします。
お客様の笑顔とワクワクするカーライフの実現が私たちの使命です。車のことなら何でもお気軽にご相談ください。

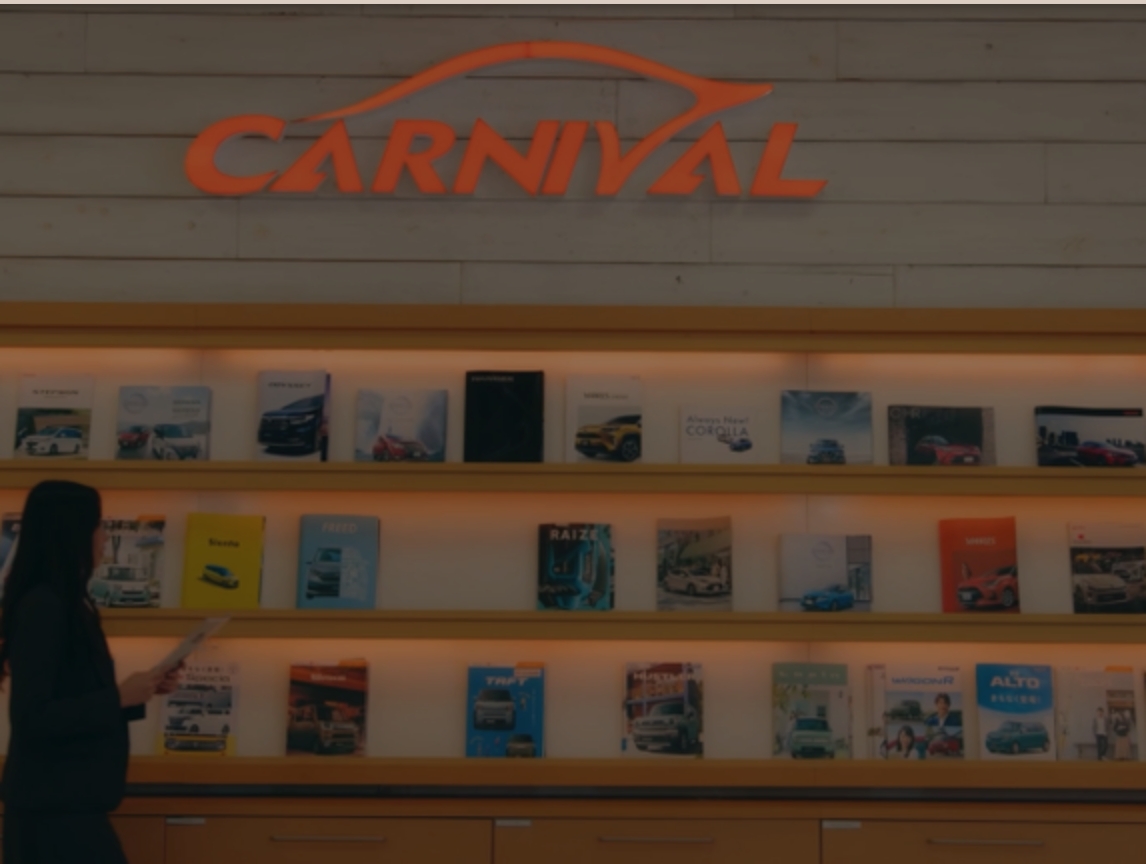
contact
お問い合わせ
お電話でのお問合わせ
最寄りの店舗に直接ご連絡お願いします
(受付時間:AM10:00~PM7:00)
メールでのお問合わせ
メールでのお問合わせはこちら